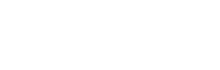特別研究
趣旨
特別史跡三内丸山遺跡は、縄文時代前期中頃から中期末の大規模な集落跡であり、円筒土器文化の解明のみならず、縄文文化の研究においても欠くことのできない重要な遺跡です。青森県教育委員会ではこれまで、三内丸山遺跡の全体像の解明及び縄文文化に関する調査・研究を進めるため、各種分析や資料の蓄積等を行うとともに、特別研究として、関連する研究を行ってきました。
研究テーマ
①三内丸山遺跡に関する研究
②円筒土器文化に関する研究
③縄文遺跡の保存・公開・活用に関する研究
(例えば遺構や出土品の展示方法、体験学習などの普及・啓発・活用に関する研究)
特別研究概要一覧
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | その他の年度 |
研究テーマ
青森県域の縄文時代中期後半~後期前半の配石墓の研究 ―三内丸山遺跡の環状配石墓を中心に―
研究者
高屋 昂平(東京大学大学院人文社会系研究科 修士課程)
研究成果概要
土坑直上に礫を環状に配した環状配石墓は、三内丸山遺跡において特徴的な遺構のひとつである。環状配石墓は、配石を持たない土坑墓とは被葬者が異なる可能性が指摘されているが、三内丸山遺跡以外においては、過去に数例挙げられているのみで、分布・特徴については不明な点が多い。
以上を踏まえ、青森県域(本州島北緯40度以北)の縄文時代中期後半~後期前半の配石墓について、形態・土坑の長軸方向・出土遺物について分析を行い、環状配石墓の位置づけと、石棺墓(縄文時代中期末~後期初頭の青森県域において特徴的な、土坑の壁に沿って礫を配した配石墓)・環状列石(後期前葉ころに出現する、礫を配して広場的な空間を構築した遺構)との関係を検討した。
分析の結果から、環状配石墓は、散発的にではあるが、青森県域全体に存在し、土坑に対し環状配石が大きいもの(1類)、土坑と環状配石の大きさがほぼ同じもの(2類)に分類できることがわかった。環状配石墓1類と2類とは、規模の差から、性格(被葬者など)に差がある可能性が高い。また、環状配石墓は、石棺墓の成立に大きな影響を与えた可能性があること、環状配石墓と環状列石は、規模・主な時期の差異から、直接関係する可能性は低いが、環状配石墓に代表される、青森県域における配石行為・埋葬行為の伝統は、環状列石に大きな影響を与えている可能性が高いことを指摘した。
研究テーマ
人類の果実利用がニワトコ属核形態に与えた影響の解明
研究者
平岡 和(北海道大学大学院文学院)
研究成果概要
円筒土器文化圏や周辺地域における現生のニワトコ(狭義)Sambucus racemosa subsp. sieboldianaとエゾニワトコS. racemosa subsp. kamtschaticaの果実・核の計測と遺跡出土の未炭化核、炭化核、圧痕資料の形態分析を実施し、核形態の体積の時空間的な差異を調べた。
現生のニワトコ(狭義)核の体積の最大値は約1.57mm3だった。エゾニワトコは北海道では1.57mm3以上の核が検出されたが、三内丸山遺跡に生育するエゾニワトコ核は1.57mm3以下だった。未炭化の出土核も1.57mm3以下であれば、ニワトコ(狭義)かエゾニワトコ、1.57mm3以上の核であればエゾニワトコである可能性が高いと考えた。さらに、エゾニワトコの方がニワトコ(狭義)より核の体積に対して果実の体積が大きい傾向があった。縄文時代の人類が核を廃棄し、果肉と果汁を利用していたならば,エゾニワトコの方が採集・利用の効率が良く、利用価値が高かったと考えた。
出土核形態を時間軸・空間軸から見ると、青森県と秋田県では、縄文時代前期頃には既に1.57mm3以上の大型の核が出土し、晩期頃から徐々に小型化した。一方、北海道では、縄文時代の出土核の大きさは中近世頃まで維持された。北海道では人類の果実利用が東北地方以南より長期間継続され、2亜種の分化に影響した可能性を指摘した。
研究テーマ
円筒土器文化圏の集落形態と変遷に関する比較考古学的研究
研究者
永瀬史人(さいたま市教育委員会)
研究成果概要
縄文時代の中でも人口が増加すると考えられている中期の集落は、関東地方では住居跡が環状にめぐる「環状集落」で構成されることが知られているが、円筒土器文化圏における同時期の集落はいわゆる「列状集落」であることを特徴とする。この集落の形態的な違いが何を意味しているのか? また、どのような点に共通性が認められるのか? 北東北・北海道と関東地方の縄文集落との比較を通じてその様相を捉えていくことを目的とする。
ここでは、円筒土器文化のいわゆる「列状集落」の中で全体的な集落の構成や変遷が確認されているいくつかの遺跡を取り上げ、その時間的変遷と時期毎の住居跡の主軸方向などを分析項目として変化の画期を検討した。
全体に共通する事項としては、中期後半以降になると住居群の分布が広場となる方向に寄る、あるいは主軸方向が広場の方向に向く、掘立柱建物群の出現が顕著になる例など、広場を意識し、利用するかのような傾向がみられ、墓にかかわる遺構が中央空間に出現するようになる。
一方で、縄文集落の形態としてよく知られている「環状集落」の変遷をみると、住居群の分布が時間の変遷と共に広場の方向へ移行する傾向があり(内進化現象)、中期後葉以降、広場となる空間に屋外埋甕群や土壙墓群、環状列石などが現れる事例が確認された。
列状集落と環状集落は北緯40°線を境に分布圏が明瞭に異なることから、その形態の違いは文化形態の差異によるものといえるが、二大群に分節された住居群と広場の空間を保持した形態、集落の変遷パターンには共通点が見いだされ、その背景に北東北や関東地方への大木系土器文化圏の波及が関与している可能性があることを指摘した。
研究テーマ
縄文人のDNAを解読する-堆積物からDNAを取り出せるか?-
研究者
山谷あかり(青森大学青森ねぶた健康研究所)
研究成果概要
日本を代表する縄文遺跡である三内丸山遺跡に暮らした縄文人のDNAが解読できれば、その情報そのものが「資料」として重要であり、今後の人類進化研究の進展に寄与する。また、縄文人のゲノム情報と今の青森に暮らす現代人のゲノム情報を比較することで、例えば、青森県が「短命県」である理由を遺伝学的な視点から考察できるかもしれない。このような考えのもと、本研究に着手した。
はじめに、三内丸山遺跡の堆積物(土壌)からのDNA抽出方法を検討した。由来の明らかなDNAを土壌に吸着させた後、抽出操作を行なった。その後、抽出液を分析し、設定した方法でDNAが抽出できることを確認した。次に、三内丸山遺跡に保管されていた埋設土器土壌をサンプリングし、土壌からDNAを抽出した。抽出したDNAに対して、配列を解析するためのライブラリ調製を行なった。シーケンスおよびデータ解析は金沢大学にて実施した(覚張隆史先生のご厚意による)。結果、埋設土器土壌サンプルから得られたDNAの中に縄文人由来だと思われるDNA配列は検出されなかった。より保管状態の良いサンプルであれば、縄文人DNAが残存していた可能性はある。今後、本研究をどのように継続するか、検討中である。
研究テーマ
三内丸山遺跡における枝回転文土器の調査と土器製作季節の推定
研究者
矢野健一(立命館大学)
研究成果概要
三内丸山遺跡の第6鉄塔地区から、縄文前期の円筒下層a~b式(約6000年前)に位置付けられる「枝回転文土器」が出土している。この枝回転文土器は、木の枝を回転させて文様を施したことはわかっているが、木の樹種はわかっていない。文様を施すために選んだ木には特別な意味があるのかもしれない。このことから、本研究では木の種類(樹種)を特定することを目的とし、検討をおこなった。また、木の先端部の芽の状態から、どの季節の枝を利用したかを推定した。
三内丸山遺跡で報告されている枝回転文土器1点について調査、及び茅野嘉雄氏のご教示により、ヤチダモという木の枝の短枝に密集する葉痕を利用していると判断した。(1)枝の先端付近の直径が1㎝近い、(2)葉痕が互生する、(3)葉痕が半円形に近く、小さな「維管束痕」が多数弧状にめぐる、(4)葉痕の縦列の間隔が短い、(5)半円形の葉痕上端中央に接するように冬芽が発芽する、といった条件を満たす枝を東北大学植物園所蔵標本の悉皆調査によって調べた結果、モクセイ科トネリコ属の落葉広葉樹であるヤチダモ以外には考えにくいという結論に達した。また、円筒下層式の枝回転文は3種に分類されているが、器面状態と施文方法を変更すれば、3種とも同一原体で施文可能であることを実験で確認した。
枝先端部の冬芽が形成されるのは夏の終わりから春先までだが、葉痕のある短枝は年間を通じて入手できるため、枝の入手季節の特定は困難である。葉痕だけではなく、冬芽自体の痕跡を有するものがあれば、秋から春先に限定できるはずである。
研究テーマ
三内丸山遺跡出土土器付着炭化物の脂質分析-前期から中期へ煮炊きは変化したのか?-
研究者
宮⽥佳樹(東京⼤学総合研究博物館)
研究成果概要
三内丸山遺跡から出土した縄文土器の内面付着炭化物に含まれる脂質(有機物)を分析することで煮沸内容物を推定し、三内丸山遺跡における土器の使い方や、食のあり方について復元を行った。
土器付着炭化物の脂質分析結果から、縄文時代前期中・後葉(円筒下層式土器)は、クリやドングリなどの堅果類、陸獣などの陸棲の動植物から、魚類や海獣類などの海棲動物まで、多様性のある食材選択を行っていた。縄文時代中期前・中葉(円筒上層式土器)になると、植物質の影響がほぼ見えなくなり、陸獣と海棲動物中心の食材選択に変化していき、中期後葉(榎林・最花・大木10 式土器)になると、陸棲動植物は検出されず、海棲動物中心の食材選択へと推移した。
バイオマーカー解析の結果、全ての時期に関して、植物質の影響は見られるものの、分子レベル炭素同位体組成からは、前期から中期にかけて、植物質の影響が小さくなり、海棲動物の影響が大きくなる傾向が伺えた。
これまで花粉分析によって、縄文時代前期から中期にかけて、クリやトチノキなど、植物利用の盛衰が指摘されていたが、煮炊き内容物の変遷を調べることにより、海産物利用が段階的に大きくなることを初めて指摘した。
研究紀要